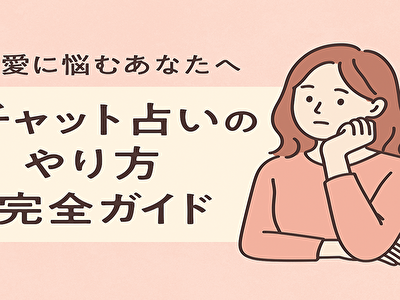はじめに
近年、連日のように報道されるクマの出没や被害ニュース。山間部に住む人々だけでなく、都市に暮らす私たちにとっても「明日は我が身」と感じさせられるような恐怖を覚える方も多いでしょう。しかし、本当にクマはそんなに危険な存在なのでしょうか?
俳優として知られる東出昌大さんは、今や現役の猟師として自然の中で生活しています。彼が語る「クマの真実」とは――。この記事では、東出さんの言葉を通して、クマとの共生のあり方を考えていきます。
東出昌大が語る「クマはそんな危ないもんじゃない」の真意とは?
東出昌大はなぜクマに対して冷静なのか
東出昌大さんは、ただの俳優ではありません。北関東で本格的な狩猟生活を送り、実際に山に出て動物と向き合っている現役の猟師でもあります。彼が語る「クマはそんな危ないもんじゃない」という言葉には、現場でのリアルな経験が裏打ちされています。クマの危険性を全否定しているわけではありませんが、必要以上に恐れるべき存在ではないというのが彼の主張です。
実際、彼が語る通り、クマと遭遇する機会は想像よりもずっと少ないのが現実です。人間がクマに出会うのは、山深い場所に踏み込んだ時や、エサを求めて人里に降りてきた一部のケースのみ。東出さんのように山に入ることが日常の人間ですら、「滅多に出会わない」と言います。この言葉は、一般の人たちが感じている「日常にクマがうようよしている」という印象が、実態と大きくずれていることを意味しています。
冷静さの理由は、クマに対する知識と経験にあります。クマは非常に警戒心が強く、人間の気配を感じるとほとんどの場合は先に逃げます。だからこそ、東出さんは「危ないもんじゃない」と断言できるのです。恐怖は無知から生まれる──そのことを彼は私たちに気づかせてくれているのです。
メディア報道とのズレを感じる理由
現在、テレビやネットニュースでは連日のように「クマ出没」「襲撃」「危険!」といった見出しが踊っています。しかし、東出昌大さんは「その報道の多くが過熱しすぎている」と語ります。実際に、彼の元にもクマに関する取材依頼が多数寄せられており、メディアが「数字(視聴率やアクセス数)が取れるテーマ」として、恐怖を強調している現実があるのです。
私たちの多くは、メディアを通じて世界を見ています。だからこそ、過激な報道が繰り返されると「クマがどこにでも出てきて、人間を襲う」という印象を抱きやすくなってしまいます。しかし実際には、そういった被害はごく一部であり、しかも極めて特殊な状況下で起きています。
東出さんは、報道の偏りが「クマ=悪者」という単純なイメージを作り出し、それが野生動物への理解や共生の道を遠ざけていると懸念しています。メディアの情報をうのみにせず、自分で考える力を持つことの大切さも、彼の発言からは読み取れます。
クマ遭遇のリアルな頻度と実態
実際に、どれほどの頻度で人間がクマに襲われているのか。環境省のデータを見てみると、例えば2025年の4月から10月までの間にクマによる被害件数は176件、被害者数は196人とされています。この数字だけを見ると確かに多く感じるかもしれません。
しかし、実はクマによる年間の死亡事故数はほぼ横ばいで、令和3年(2021年)は5人、平成28年(2016年)は4人と、ここ10年で大きく増えているわけではありません。これは、東出さんが述べているように「メディアの報道量が増えていること」によって、あたかもクマ被害が爆発的に増えているように錯覚してしまうだけなのです。
また、交通事故の死亡者数は年間2000人を超え、自殺者数に至っては2万人以上。しかしこれらの数字は「しょうがない」と片付けられ、注目されにくい現状があります。一方で、クマによる数件の事故はセンセーショナルに報道される。このアンバランスこそが、恐怖を増幅させている大きな要因なのです。
死亡事故の数字から見える現実
死亡者数のデータを見ると、クマによる被害が一部に偏っていることがわかります。つまり、山間部や里山など、人間とクマの生活圏が接している一部の地域でのみ起こっているのです。そして、ほとんどの場合、クマは「突然の遭遇」でパニックになり、防衛的に攻撃を仕掛けるケースがほとんどです。
つまり、クマが好戦的で人間を意図的に襲っているわけではなく、「怖がって攻撃する」というのが実態です。東出さんもこの点に注目し、「正しい知識を持てば、クマを必要以上に恐れなくて済む」と語っています。
確かに、クマとの接触はリスクを伴いますが、それは他のリスクと比べて特別大きいわけではありません。冷静に数字を見て、過剰な恐怖心から距離を置くことが、共生の第一歩になるのです。
恐怖を煽ることで数字を取るメディアの手口
現在のメディアは、クリック数や視聴率を重視する構造になっています。そのため「衝撃的」「怖い」「異常」というキーワードはとても強く、クマのような「リアルな恐怖」を扱う話題は大きな関心を集めやすいのです。
東出昌大さんは、メディアが「クマは数字が取れる」と気づいた瞬間から、報道が過熱したと指摘しています。確かに、クマに関するセンセーショナルな映像や写真はインパクトがあり、人々の想像力をかき立てます。
「血まみれ」「襲撃」「阿鼻叫喚」──そういった言葉が並ぶことで、現実以上に「怖さ」が膨れ上がっていきます。しかし、実際に山に入っている東出さんのような人からすれば、そうした報道はあまりに現実離れしているというのです。
情報の受け手として、私たちができることは何でしょうか?それは、一度立ち止まり、「本当にそうなのか?」と考えること。事実に基づいた情報を得て、正しく恐れる姿勢が求められています。
クマ出没が増えた背景にある2つの要因
どんぐりなどの木の実が不作になっている理由
クマが人里に出没する理由のひとつに、山の中での「食べ物不足」があります。クマの主食は意外にも肉ではなく、木の実や果物。特に秋になると、どんぐりやブナの実といった「堅果類(けんかるい)」をたくさん食べて冬眠に備えます。
しかし、近年ではこの堅果類が不作になる年が増えています。その原因は気候変動や異常気象による影響が大きいと考えられています。たとえば、夏の猛暑や長引く雨、逆に雨不足などがあると、木が実を十分に育てられなくなってしまうのです。これは人間の農作物と同じで、自然界の作物も天候に左右されるのです。
また、山の開発や林業の縮小などによって、生息地や食料の分布が変わってしまったことも要因です。森が荒れて手入れされなくなると、クマがエサを見つけにくくなり、人間の住む場所にまで下りてきてしまうことがあります。
クマにとって人里は決して快適な場所ではありません。それでも出てくるということは、よほど山に食べ物がないからなのです。この背景を知らずに「クマが怖い、危険だ」とだけ言うのは、クマの立場を無視しているとも言えるでしょう。
クマが人里に降りてくるメカニズム
クマが山から里へと降りてくる流れには、自然な理由があります。先ほど述べたように、山にエサがない年には、クマたちは生きるためにエサを探して移動せざるを得ません。そしてエサのにおいに誘われて、果樹園や畑、ごみ置き場などに近づいてくるのです。
また、クマはとても賢く、記憶力も優れています。一度人間の場所で食べ物を見つけると、「ここに来ればまた食べ物がある」と覚えてしまいます。そうすると、同じ場所に何度も現れるようになり、出没が習慣化してしまうのです。
さらに、クマは夜行性で、夜間や早朝に行動することが多いため、人間が気づかないうちに集落のすぐ近くまで来ていることもあります。最近は防犯カメラやドライブレコーダーなどの普及により、出没が「可視化」されたことで、余計に目立つようになっている面もあります。
私たちができることは、クマを寄せつけない環境づくり。生ゴミの管理や果樹の手入れなど、小さな対策を積み重ねることで、クマが人里に来なくても済むようにすることが重要です。
猟師の高齢化がもたらす影響とは
東出昌大さんが特に問題視しているのが、猟師の高齢化です。環境省のデータによると、狩猟免許を持っている人の約70%が60代以上。東出さんの所属する猟友会でも、70代、80代の方が中心で、60代ですら「若手」と言われる世界なのです。
高齢化が進むと、山を歩き回って動物を探すのが困難になります。昔は山の奥まで入って狩りをしていた猟師たちも、今では道路沿いでの“流し猟”が主流。これは車に乗って動物を探し、道路脇で銃を撃つ方法で、法律的にはグレーな面もあります。
また、大きなシカなどを仕留めたとしても、年配の猟師一人では軽トラックに載せられず、その場に放置してしまうこともあるそうです。これは本来違法行為ですが、「駆除の効率を優先せざるを得ない」という現場の苦悩もあります。
このような状況が続くと、山の管理機能が低下し、結果としてクマなどの野生動物の行動範囲が拡大してしまうのです。若い猟師の育成が急務だと東出さんは訴えています。
若い猟師が少ない現状と課題
日本の狩猟業界では、若手不足が深刻な問題となっています。昔は家業として受け継がれることも多かった猟師の仕事ですが、今では「危ない」「収入にならない」「都会に出たい」といった理由で、若者の関心は薄れているのが現状です。
一方で、東出昌大さんのように「自然と向き合う暮らし」に魅力を感じて狩猟を始める若者も、少しずつ増えてはいます。しかし、狩猟免許の取得や装備の購入、地域の猟友会への参加など、始めるまでのハードルが高いことも事実です。
また、猟師として活動を続けるには、地域との信頼関係や経験の積み重ねが不可欠です。野生動物の命を扱う仕事には、知識・技術・責任が求められます。単なる「サバイバルゲーム」とは全く異なり、深い倫理観が必要なのです。
このような背景を理解し、若い世代が「森を守る担い手」として参入しやすい環境づくりが求められています。東出さんのようなロールモデルの存在が、その一歩を後押ししてくれるはずです。
自然と人間社会のバランスが崩れている?
クマ出没の問題は、単なる「動物が危ない」という話ではありません。背景には、自然と人間社会の関係性の崩れがあります。山の手入れがされなくなったこと、猟師の減少、都市への人口集中──こうした人間の暮らしの変化が、野生動物の行動に影響を与えているのです。
また、気候変動や自然災害の増加も、野生動物の生息環境を不安定にしています。昔は人と動物がそれぞれの領域を守りながら共存していましたが、今ではその境界があいまいになり、トラブルが起きやすくなっています。
東出昌大さんが指摘するように、「クマを悪者にするだけでは問題は解決しない」のです。私たちが自然との向き合い方を見直し、共に生きる方法を探ることが、真の解決策となるでしょう。
猟師が語る「クマの生態と本来の姿」
クマは本当に人間を襲うのか?
「クマは人間を見つけたらすぐに襲ってくる」と思っている人は多いかもしれません。しかし実際には、クマはとても臆病な動物です。山でクマとばったり出会ったとしても、クマの方が驚いて先に逃げることがほとんどです。東出昌大さんも、長年山に入っていてクマに遭遇する機会はごくわずかだと語っています。
クマが人間を襲うケースは、非常に限られた状況でのみ起こります。たとえば、自分の子ども(子グマ)を守るためだったり、冬眠前に空腹で極度にストレスを感じていたりしたときです。あるいは、突然近づきすぎてしまった場合や、驚かせてしまったとき。つまり、クマは「敵から身を守るために攻撃する」のであって、積極的に人間を狙って襲う動物ではないのです。
この事実を知らずに「クマ=人を襲う怖い生き物」と思い込んでしまうと、本来なら避けられるトラブルも増えてしまいます。だからこそ、東出さんのような現場を知る人の声に耳を傾け、正しい知識を持つことが大切なのです。
クマが人間を避ける習性について
クマは本能的に人間を恐れています。人間の存在を感じ取ると、クマは自分からその場を離れようとします。これは野生動物としての自然な行動です。だからこそ、多くのクマは人が多く出入りする登山道やキャンプ場の近くでは活動を控える傾向があります。
実際、山を歩いていてクマと出会った人の多くが「クマがすぐに逃げた」と証言しています。これは、クマが人間との無用なトラブルを避けるためにとっている賢い行動です。東出さんも「本当に遭遇する確率は低い」と断言しているように、クマは人の気配に非常に敏感なのです。
ただし、クマが人間を避けなくなってしまうケースもあります。それは、人間の生活圏で「おいしいエサがある」と学習してしまったときです。人間の食べ残しや生ゴミなどを何度も経験すると、クマは人の存在に慣れてしまい、距離感が狂ってしまうのです。
このような「人慣れ」したクマが増えると、逆にリスクは高まってしまいます。だからこそ、私たちがクマを近づけない生活環境を整えることも、クマとの共存には欠かせないのです。
クマの行動パターンとその意味
クマの行動には、明確なパターンと理由があります。まず、クマは基本的に夜行性で、昼間は静かな場所で休んでいます。そして、早朝や夕方に活動を始め、食べ物を探すのが習性です。この時間帯に山に入ることで、思わぬ遭遇のリスクが高まります。
また、クマは季節によって行動が大きく変わります。春は冬眠から覚めてエネルギーを補うため、草や新芽を食べて活動を再開します。夏には果物や昆虫、小動物なども食べ、秋になると冬眠に向けてとにかくたくさん食べて体に脂肪をため込みます。これを「食いだめの季節」と言います。
このように、クマの行動は「どう生き延びるか」を考えた合理的なもので、決して無意味に動いているわけではありません。人間にとって脅威に感じる行動でも、クマにとっては単なる生存のための動きなのです。
東出さんが語るように、「動物の行動には必ず理由がある」という視点を持つことが、正しい理解と接し方への第一歩になるのです。
クマと適切な距離を保つ方法
クマと安全に共存するためには、物理的にも心理的にも「距離感」を保つことが大切です。まず、山に入るときは必ず「音を出す」こと。クマ鈴やラジオを使って、人間の存在をクマに知らせるのが基本です。そうすれば、クマの方から避けてくれます。
次に、食べ物の管理も重要です。キャンプや登山での食べ残し、生ゴミをそのままにすると、クマが寄ってくる原因になります。においを発するものは密封して持ち帰るか、専用の保管箱を使いましょう。
また、クマの痕跡(足跡やフン、爪痕など)を見つけたら、その場から離れることが鉄則です。無理に近づいたり、写真を撮ろうとするのは非常に危険です。クマとの遭遇は「避けること」が最も有効な対策なのです。
東出さんのように、クマの習性を知って行動すれば、リスクは大幅に下げることができます。「怖いから近づかない」ではなく、「正しく知って、正しく距離を取る」。この考え方が、これからの時代には必要とされているのです。
クマに出会ったときの正しい対処法
もし、運悪くクマと出会ってしまった場合、どうすればよいのでしょうか?そのときに最も大事なのは「落ち着くこと」です。驚いて大声を出したり、走って逃げたりすると、クマの警戒心を刺激し、攻撃に繋がる危険性があります。
まずはゆっくりと後ずさりしながら、その場を離れましょう。視線をクマから外さず、急な動きを避けるのがコツです。クマが立ち上がった場合、それは「攻撃の前触れ」ではなく、相手をよく見ようとしているだけです。こちらを確認して、興味がないとわかれば多くは去っていきます。
それでもクマが向かってきたら、「クマ撃退スプレー」が非常に有効です。これを携帯している登山者は少ないですが、クマの生息地に入るなら必携のアイテムと言えます。万が一に備えて、使い方を事前に確認しておくと安心です。
一番の対処法は「出会わないこと」。そして、もし出会ってしまっても、正しい知識があれば冷静に対処できます。東出昌大さんが伝えたいのは、まさにこの「知識が命を守る」というメッセージなのです。
東出昌大が訴える「狩猟現場のリアル」
現場で起きている問題とは
クマの出没や被害が報道される一方で、あまり知られていないのが「狩猟現場の現実」です。東出昌大さんは、山に通い、実際に獲物を仕留める現場に立っている数少ない芸能人のひとり。彼が語る現実は、都市に住む私たちが想像する“自然のイメージ”とはまったく違います。
たとえば、山奥でシカやイノシシを仕留めても、道がない場所からは運び出すのが困難です。山道を何キロも歩いて獲物を担ぐ作業は、体力も時間も必要で、猟師たちは日々過酷な環境の中で活動しています。また、撃った動物を安全に処理するための技術や道具も必要です。野生動物は病気や寄生虫を持っていることもあるため、処理を間違えれば食品衛生にも関わってきます。
さらに、最近では獲った動物の肉を販売する「ジビエビジネス」が注目を集めていますが、その背景には複雑なルールや規制があり、個人の猟師が参入するには大きなハードルがあります。つまり、「猟師をやる=自然と向き合う素朴な暮らし」というイメージだけでは語れない、リアルな課題が山積しているのです。
違法な“流し猟”と獲物の遺棄の実態
「流し猟」とは、車で山道を走りながら動物を見つけ、道路脇から銃を使って仕留める狩猟スタイルです。法律的には「車の中からの発砲」や「死骸の遺棄」は禁止されていますが、現場では暗黙の了解として黙認されているケースもあります。
東出さんの話によると、高齢の猟師が増えるなか、山を歩いて狩りをするのが困難になり、流し猟が主流になってきているそうです。道路脇で撃ったシカを運び出せずにそのまま放置するという状況も実際にあるといいます。これは明らかに法律違反であり、倫理的にも問題です。
こうした実態は一般にはほとんど知られておらず、「猟師=自然の守り手」という美しいイメージだけが広がっています。しかし、現場には厳しい現実があり、理想と現実のギャップに苦しむ猟師も少なくありません。
東出さんは、違法行為を容認するわけではありませんが、「そうしなければ対応しきれない現場の事情もある」とも述べています。法の厳格な運用と、現実に即した柔軟な対応の両方が求められているのです。
高齢化による狩猟方法の変化
現在、狩猟免許保有者の70%以上が60代以上というデータがあります。これは日本の少子高齢化を象徴するような状況ですが、狩猟の現場にも深刻な影響を及ぼしています。
高齢の猟師は、体力や視力が落ちているため、昔のように山を歩いて狩りをするのは難しくなっています。その結果、車を使った流し猟や、罠を道路脇に仕掛けるといった「効率重視」の方法が増えてきました。
また、仕留めた動物を運搬できずに山に放置するケースも増えており、それがカラスや他の動物を呼び寄せる原因にもなっています。つまり、狩猟のやり方が変わったことで、山の生態系にも影響を与えているのです。
若い世代が狩猟に興味を持たなければ、この状況はますます悪化するでしょう。東出さんのような若い世代が現場に入り、正しい知識と技術を持って活動していくことが、日本の自然環境を守るうえで重要になっています。
法と現実のギャップをどう埋めるか
狩猟に関する法律は、人間と自然の安全を守るために整備されています。しかし、現実の現場では、その法律が必ずしも守られていないこともあります。それは単に「法律を無視している」というより、「法律通りにやっていたら、実際には仕事にならない」という側面があるからです。
たとえば、流し猟のように違法とは知りながらも、それ以外の方法では高齢の猟師が活動できない現実。罠を設置するにも山奥に入る体力がないため、道路脇に設置せざるを得ない事情。これらは単なるルール違反ではなく、制度と現場の乖離によって生まれた矛盾です。
東出さんは、法律を変えることよりも「現場に合った柔軟な運用」や「サポート体制の整備」が必要だと訴えています。たとえば、獲物の運搬支援、狩猟者の安全対策、若者の参加促進など、制度の見直しと現場の声を結びつける取り組みが求められます。
現実を知らずにルールだけを押し付けても、問題は解決しません。大切なのは、現場の声に耳を傾け、現実を見据えた制度を構築することです。
若い猟師が必要な理由とは
東出昌大さんが繰り返し訴えているのは、「若い猟師の存在が必要不可欠だ」ということです。高齢の猟師だけではもう限界がきており、山の環境や動物たちのバランスを保つには、若い力がどうしても必要なのです。
若者の参加が進めば、山奥にも積極的に入れるようになり、獲物を適切に処理して持ち帰ることが可能になります。また、若い世代が持つ発信力を活かして、狩猟の現実や野生動物の情報を社会に伝えることもできます。
しかし、猟師になるには装備や資格の費用、地域との関係性、さらには命を扱う責任と覚悟も必要です。東出さんのように「自然と向き合うこと」の意味をしっかり理解し、現場で行動できる人材が求められています。
狩猟は単なる趣味ではありません。自然と人間の共存を支える、重要な仕事です。東出さんのような存在が、今後の日本の自然環境を守るための「キーパーソン」になっていくでしょう。
クマと共生する社会を目指して
恐怖ではなく理解から始めよう
クマという存在を考えるとき、多くの人はまず「恐怖」を思い浮かべます。しかし、東出昌大さんが伝えようとしているのは、「まずは理解することの大切さ」です。クマは確かに大きな体と鋭い爪を持つ野生動物で、接し方を間違えると危険な存在です。しかし、その反面、非常に臆病で繊細な生き物でもあります。
山でクマと出会った人の多くが、「逃げていった」「こちらを避けようとした」と語っています。クマは本能的に人間を警戒し、できるだけ距離を保とうとします。むやみに攻撃してくるわけではないのです。
メディアの報道が恐怖心をあおることで、クマに対する誤解が広がってしまいます。その結果として、必要以上に駆除が進んだり、本来の生態系が崩れてしまったりするリスクもあるのです。恐怖ではなく、まずは「なぜクマが行動しているのか?」を理解すること。それが、共生の第一歩です。
正しい情報発信の必要性
現代は、誰もがスマートフォンでニュースを見たり、SNSで情報を発信したりできる時代です。だからこそ、「正しい情報を見極める力」と「偏った報道を疑う視点」がますます重要になっています。
クマに関する報道は、しばしば過激な表現で恐怖を煽る傾向にあります。「出没」「襲撃」「パニック」といった言葉が並ぶと、冷静に物事を見られなくなってしまいます。しかし実際には、東出さんのような猟師の声や、環境省のデータを見れば、クマによる死亡事故が急増しているわけではないことがわかります。
私たち一人ひとりが、情報を鵜呑みにせずに「なぜそう言われているのか?」と考えることが大切です。そして、できれば信頼できる専門家や現場の声に耳を傾けてみましょう。情報の質が変われば、見える世界も変わります。
教育とマナー啓発の重要性
クマとの共生を目指すには、「教育」と「マナー」が欠かせません。たとえば、学校の授業や地域の講習会などで、野生動物との距離の取り方や、出会ったときの対処法などを学ぶ機会があると、子どもたちの意識も変わっていきます。
また、登山やキャンプなど自然に触れる場では、大人にも正しいマナーの啓発が必要です。ゴミを放置しない、クマのエサになるものを放置しない、鈴やラジオで音を出して行動する──こうした基本的なルールを守るだけで、クマとの不要な接触は大幅に減らすことができます。
自然は「利用する」ものではなく、「共にある」もの。人間の一方的な都合で動物たちの生活を脅かしてはいけません。東出さんのように、自然と真摯に向き合う姿勢を持つことが、これからの時代に求められているのです。
人間が自然にどう向き合うべきか
都市化が進み、便利さを追求する現代社会のなかで、私たちは「自然とどう向き合うか」という問題から目を背けがちです。しかし、クマの出没や野生動物による農作物の被害など、自然と人間のバランスが崩れている今、避けては通れない課題になっています。
自然を単なる「リスク」として排除するのではなく、その中でどう共存していくかを考える視点が必要です。人間だけが優先される社会ではなく、他の生き物たちの存在も尊重する社会こそ、持続可能な未来に近づく道です。
東出さんは、自然と向き合うことで、自分の中の「命への向き合い方」も変わったと語っています。自然の中で生きることは、便利さとは逆の、不便で厳しい世界かもしれません。しかしそこには、人間が本来持っていたはずの「謙虚さ」や「感謝」があるのです。
東出昌大の言葉から考える未来
「クマはそんな危ないもんじゃない」──この言葉には、東出昌大さんの経験と想いが詰まっています。彼はクマを美化しているわけでも、軽視しているわけでもありません。むしろ、現実を見たうえで「恐怖だけで語るのは違う」と私たちに問いかけているのです。
この記事を通じて、私たちは一方的な恐怖や偏見を手放し、「どうすれば自然と共に暮らせるか」を考えるきっかけを得られたのではないでしょうか。東出さんのように自然と真正面から向き合い、自分にできることを探していくこと。それがこれからの社会に求められる姿勢です。
自然は敵ではなく、共に生きる仲間です。クマという存在を通じて、私たちの「自然観」や「生き方」そのものが問われているのかもしれません。
まとめ
この記事では、俳優であり現役猟師でもある東出昌大さんが語った「クマはそんな危ないもんじゃない」というメッセージをもとに、クマの実態や報道とのギャップ、狩猟現場の現実、共生の道などを紹介しました。
クマに関する報道が過熱する中、私たちに必要なのは「正しい恐れ方」と「理解」です。現場に立つ東出さんだからこそ見えるリアルな視点から、クマとの距離の取り方、自然との向き合い方、そして人間社会のあり方まで、多くの気づきを得ることができます。
野生動物をただ恐れるのではなく、正しく知り、適切に接する。自然とのバランスを取りながら生きていく知恵と姿勢が、これからの時代にはより求められていくでしょう。